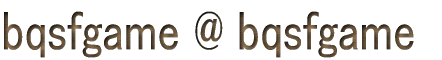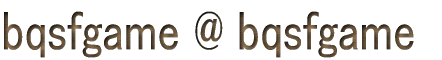
バーバリアンキングス
Barbarian Kings / SPI / Ares #3
一言で言えば‥‥
コンパクトながら必要なすべてが含まれた魔法の国の陣取合戦
惑星ハイパスティアのキャスタフォン大陸における赤の時代のキャンペーン
こんなゲーマーにお薦めしたい
手応えが十分あってプレイアブルなファンタジー戦争ゲームを求めるプレイヤーに
プロットや資金管理などのブックキーピングが苦でないプレイヤーに
| プレイ人数 | 2−5人 |
| プレイ時間 | 2〜5時間 |
| ルール難度 | 初級ウォーゲーム |
| デザイナー | グレッグ コスティキャン |
| 入手状況 | 英語版は中古市場で発見可能 |
バーバリアンキングスに想う
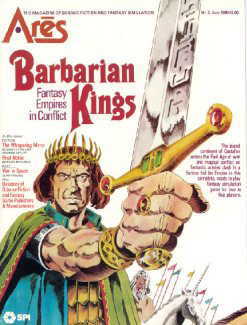
バーバリアンキングスは,SPIが発行していたSF/Fゲームの専門誌「Ares」の3号の付録ゲームとして発表されました。
Aresの1号はサイモンセンの作であり,2号はダニガンの作です。そして,3号で登場したのが,コスティキャンでした。今にして想えば,なんとも豪華なラインナップです。SF/Fゲームの専門誌が,このような豪華なラインナップで発行されることは,少なくともわたしが死ぬまでの範囲では,二度とあり得ないのではないかとさえ思います。
バーバリアンキングスは,雑誌版の他にボックス版も発行され,日本にも訳付きで入ってきました。その後,TACTICS誌の付録ゲームとしても再録されました。このため,ウォーゲームに本格的に取り組んでいたプレイヤーであれば,広い世代範囲にわたって,多かれ少なかれこのゲームを見かけたことがあるはずです。
わたし自身は友人が持っていたボックス版を良くプレイしました。当時は,まだ誰もゲームの所有数が一桁からようやく二桁に掛かるような時代で,他に適当な演目がなくなると,このゲームが良くプレイされました。プレイされた理由は,プレイ人数の範囲が広く,その場で説明してもできるルール分量で,それでいてプレイすると十分に歯ごたえがあったからでしょう。
ただ,その割りには,このゲームの世評を聞く機会は多くありません。後のゲームに追い越されてしまったからだろうか‥‥などと思ったりもしていました。ところが,今回,この紹介を書くにあたって実に十数年ぶり(ほぼ二十年に近い)にプレイしてみたところ,案に相違して面白いのです。気になるところもないではありませんが,今なお鑑賞に耐え得る傑作と思いました。
おそらくこのゲームを死蔵しているプレイヤーは多いであろうから,その人たちにバーバリアンキングスを見直してもらうためにも,ここで紹介しなければと思った次第です。
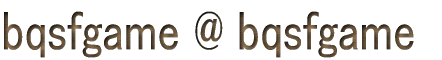
オールインコンパクトな傑作ゲーム

バーバリアンキングスは冒頭に書いた通り,赤の時代のキャスタフォン大陸での戦役を扱ったシミュレーションゲームです。
シミュレーションとは言っても,題材についての情報は筆者の知る範囲では他になく,自己説明型の架空シミュレーションゲームであり,その意味ではコスティキャンの他の作品,たとえば「SWORDS & SORCERLY」や,「DARK EMPEROR」と同様です。
設定はともかくとして,このゲームはAres初期のコンパクトなコンポーネントにまとめられています。クォーターサイズのマップに,100ユニット,ルールもチャートなども合わせて8ページです。
ところが,たったこれだけの中にファンタジー戦役を扱うゲームとして入っているべき要素はすべて含まれています。
たとえば,ファンタジーゲームならではの様々な種族が登場します。そして,そのそれぞれは独自の個性を持っています。写真の中央下部の黄色いユニットはいわゆる文明国のユニットで,強力であるが建造するのが高価で,特に森林では重装備が過ぎて無力です。中央上部にいるオレンジ色のユニットはオークで,彼らは安価であり序盤から容易に大量に購入できる。その一方で,プレイヤーの財政基盤がしっかりしてくる中盤以降では戦力の不足が明らかになり役者不足となって行きます。右側の森林の中にいるのはエルフ,左側の山の中にいるのはドワーフ,さらにその左側の赤いユニットは蛮族です。
特に面白いのは,こうした諸要素が,単にカタログスペックでなく,プレイした時にヴィヴィッドに輝いてくるところです。オークの序盤での優勢と中盤以降の停滞,文明諸国の序盤での立ち遅れと,中盤以降の重要化などは,単なるカタログ値ではなく,プレイした時に始めて理解されてきます。
ファンタジーゲームとしては魔法が欠かせません。このゲームには,わずか8ページの中に4系列からなる魔法体系が盛りこまれていて驚かされます。精神魔法,精霊魔法,幻影魔法,ネクロマンシーです。それぞれに性格が異なっていて,どの系列を学ぶかは悩ましいところです。魔法の体系はシークエンスに折りこまれていて使うタイミングがはっきりしています。とかくこのテのゲームの魔法は,ルール的に曖昧さや矛盾を生じがちなので,良く考えてデザインされていると言って良いでしょう。
陣取りゲームの常ですが経済戦争としての側面も非常に強いゲームです。エリアごとに徴税額が設定されています。また,部隊ごとに建造費と維持費が設定されています。このため,プレイヤーは毎ターン国家予算に頭を悩ませねばなりません。
特に悩ましいのはユニットの購入です。なにせ100ユニットのゲームなので,部隊ユニットのコマはすぐに枯渇してしまいます。特定の種族の特定のユニットが欲しければ早いもの勝ちです。その一方で,特定の種族のユニットは,その種族の故郷でしか徴用できません。このため,後の部隊構成のためにも特定の地域への侵攻を考える必要があります。
順番が逆になりましたが,プレイヤーの分身である王は,3つの能力を選ぶことができます。選べる能力としては4つの魔法体系のほかに戦闘指揮,後退技術,行軍指揮などの軍司指揮能力があります。これによって各プレイヤーの部隊は,構成部隊のみならず指揮官によっても個性付けされます。
実際にプレイしてもらえばわかりますが,魔法,経済,地域特性,部隊特性,指揮官特性などはどれもそれなりの重要度を持っており,また互いに関連しています。このため,コンパクトでありながら,実に考える要素が多いゲームです。このため,手応え十分なのです。
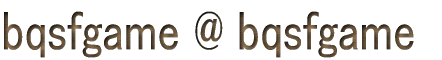
バーバリアンキングスの難点
このゲームの難点は,ブックキーピングが多いことです。
プレイヤーの資産管理のほかに,魔法の一部がプロット式です。なにより大きいのは,基本的には移動がすべてプロット式であることです。
おそらく移動がプロットと聞いたところで投げ出すプレイヤーが近年は多いのではないかと懸念します。ですが,実際にプレイしてもらうと,このゲームのプロット式の採用は,十分に労力の対価に見合う醍醐味を与えてくれていると納得が行くはずです。
まず移動できるユニットは指揮官のいるユニットだけで,指揮官が非常に高価なため実は移動するユニットの数は左程は多くありません。マップが狭いため移動の自由度もそれほど高くありません。その一方で,マルチの陣取りゲームをやったことのあるプレイヤーならわかってもらえると思いますが,こうした少数の移動部隊でエリアを取り合っていくゲームでは,移動プロットの駆け引きは,本当に悩ましいものです。相手の出方を諸事情から推察し,それに対して最善の策を練る,あるいは奇策を打つのは,まさにエリア式の陣取りゲームの醍醐味中の醍醐味です。
このゲームでは,これに絡んで魔法が存在するため,作戦的選択肢が広く,また流動的になっています。そのため,ゲームがデッドエンドに陥りにくくなっており,その一方で魔法が成功するかどうか次第と言ったところもないではありません。
そうした意味で,ブックキーピングに対する免疫があるプレイヤー,確実性の低い魔法に戦況がしばしば決定的に左右されることを許容できるプレイヤーでないと,辛い部分が少しずつあるかも知れません。
とは言え,このゲームはコスティキャンの傑作です。特にプレイアブルであるということでは,同じ路線の「S&S」や「ダークエンペラー」よりも高く評価されても良いのではないかとさえ思います。
少し誉め過ぎでしょうか‥‥?
実は,今回の撮影のためにコマをマップに両面テープで貼ってスキャナー取りこみしたのですが,間違って貼って剥がせるポストイットタイプでなく普通の両面テープを使ってしまい,一部のユニットとマップの一部を破損してしまいました。プレイに支障があるほどではないのですが,今回プレイしてみて傑作であることを痛感したので,保存用にもう1セット買おうかと思っているほどです。少なくとも,わたしにとってはこうした保存用投資を考えても良いくらいの評価のゲームです。
関連ゲーム / 類似ゲーム
コスティキャンのオリジナル設定のファンタジー戦役ゲームとしては,SPI時代の大作ソーズアンドソーサリーがあります。この他にAHから出版されたダークエンペラーもコスティキャンです。
SPI時代のコスティキャンのコンパクトな傑作としては,このゲームと共にシーボイガン市を食った怪物が挙げられます。こちらはファンタジー陣取りは趣きが異なり,いわゆるゴジラムービーのゲームで,様々な怪獣が都市を襲うゲームです。
また,Ares全体についてはAresを覚えていますか?を是非ともご参照ください。