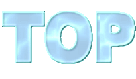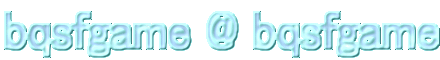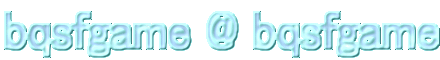
バトルフリートマーズ
Battle Fleet Mars / SPI
一言で言えば‥‥
21世紀、火星の資源に依存する地球、その火星からの物資の流入を牛耳る巨大企業、エアリーズ
だが火星の殖民労働者たちは、巨大企業の搾取に対して立ち上がった!
In 21st century, the Earth is dependent on Martian resources which is solely controlled by congromarit Ares.
But, martian colonists decides to protest Megapower Ares.
| プレイ人数 | 2人 |
| プレイ時間 | 3〜6時間 |
| ルール難度 | 中級ウォーゲーム、ただし独創的 |
| デザイナー | B.Hessel, R.Simonsen |
| 入手状況 | published in 1977 |
太陽系内紛争を描いた古典的名作
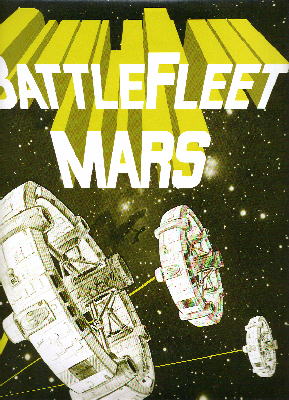
「バトルフリートマーズ」は、太陽系内の紛争を描いた古典的名作です。SPIの1977年の作品で、「インペリウム」や、「フリーダムインザギャラクシー」と言った後続の傑作SFゲームが登場してくるまでは、SFゲームの人気ナンバー1の座に君臨していた作品でもあります。
ところが、残念なことに日本語版、もしくは正規の日本語訳を付けての本格販売がされなかったため、「インペリウム」や「フリーダムインザギャラクシー」ほどには日本での認知度は高くありません。とても残念なことです。
デザイナーは、ブラッド・ヘッセルとレドモンド・サイモンセン。そしてデベロップメントは、グレッグ・コスティキャンです。SPIの黄金時代の錚々たる顔ぶれと言えます。と言っても実はコスティキャンは、この作品がSFゲーム初登板。今でこそSFゲームの鬼才のイメージの強いコスティキャンですが、そのSFデビューはヒストリカルよりも遅れて、この作品だったのです。
バトルフリートマーズは、太陽系内に版図が広がった近未来、21世紀を舞台にしています。思えば、その21世紀が既に到来している訳で、時の流れを感じます。このゲームの歴史では地球はその資源を火星に依存するようになっています。そして、その火星からの資源の流入を全て牛耳っているのがスーパーコングロマリット、エアリーズ社です。後にSPIのSF/Fの専門誌のタイトルにもなる近未来のSPI未来史の重要な存在です。
彼らは火星の殖民労働者を搾取し、地球の消費者からも利益をあげているのです。しかし、長年の搾取についに火星の労働者は立ち上がりました。外惑星や、小惑星帯も連動してのエアリーズ社に対しての反乱です。最初、地球世論は搾取された労働者の行動に同情的な流れでした。けれども、実際に火星からの物流が途絶えて市民生活に深刻な影を落とし始めると、世論は徐々に騒乱の長期化に対して敵意を持つようになってきました。ついには、それは地球に生まれたものたちと、地球でない星で生まれたものたちの遺恨へと変わっていったのです。
バトルフリートマーズのシステム
「バトルフリートマーズ」のシステムは、非常に独特です。
実際の太陽系内での慣性移動の物理的な問題をきちんと表現しているのです。このゲームが出版された1970年代のシミュレーションゲームの姿勢として、「シミュレーション」であることに力点があります。
具体的には太陽系内の惑星は、外側の惑星ほど、軌道の間隔がどんどん広くなっていきます。このため、普通のヘクスマップで描こうとすると、内惑星と外惑星はとても同じスケールでは扱い切れません。また、現実問題として、惑星の位置するポイント以外の宇宙空間は、正に空間としての意味しかありません。そこでの遭遇戦は、藁の山の中の針を探すより非現実的な試みです。
このため、このゲームでは惑星の軌道が円で描かれ、毎ターンの位置がドットで示されているだけです。宇宙船の移動は、この現在位置のドットから発進して、目標の惑星の到着未来位置へと向けてプロットされ、必要な航行期間を算出されるものとなっています。
このときに宇宙空間では等速航行ではなく、等加速度航行を行うことが前提となっています。このため、1ターンで航行できる距離を1としたときに、2ターンで航行できる距離は4になっています。さらに、このことを利用して、いわゆるフライバイができるようになっています。つまり中継点の惑星の重力場を利用して航行日程を詰められるのです。
ここまで熱心に説明してきたのですが、ハードSFや天文学が好きでない人にはピンと来ないかも知れません。けれどもわかって欲しいのは、「バトルフリートマーズ」はそうしたとっつきの悪いサイエンティフィックな部分のシミュレーションをきっちりとやっている作品だと言うことです。近年、「ゲームとして取り扱う」ゲームデザインの進歩が進んで、対象の物理現象をそのままボードに移そうというゲームは少なくなりました。
その意味でこの時代のSPIゲームは、今となっては異色の力作と感じられます。でも、あの頃はこういう取り組みが普通だったし、ゲーマーも物理現象がきちんと再現されていないと文句を付けていた時代だったように思います。
実際のゲーム展開では、まず反乱軍側が地球以遠の諸星系で反乱を起こします。地球側は、一旦、残された船を地球に集積します。この後、ゲームシステムが非常に重要な意味を持ってきます。地球側は強力な船を太陽系の中心に位置する地球にまとめて持つ状況になります。これに対して反乱軍はその外側に散在する基地を守らねばなりません。このときに地球側は好きな方向に向かって進軍することができ、またフライバイを使って進路を急変することができます。ところが外側に位置する反乱軍はこれに対して柔軟に対処することができません。外側に位置する惑星同士は距離が遠く、また一旦、ある惑星から他の惑星に増援を出してしまうと、反転することは容易でありません。
こうした太陽系内の慣性航行の力学的問題の悩みを描き出したSF小説として、谷甲州の航空宇宙軍史があります。このシリーズでも正に外惑星(こちらでは木星が主役になります)が内惑星に対して反乱します。正直に言って、ゲームのテイストやジレンマは、このシリーズに非常に良く似ています。
一頑張りして、もっと外側の惑星まで加えてプレイすれば、このシステムで航空宇宙軍もシミュレートできるかも知れません。あるいは逆に、谷甲州さんがこのゲームからヒントを得てシリーズを書いた‥と言われても「そういうこともあるかも‥」と思ってしまうほどです。
物理運動のところに力点を置いて説明しましたが、これ以外にも政治のルールが重要です。特に両陣営の世論を示すチャートと、その動向により変化するイベントチャートはゲームの展開をストーリーメイキングしていて秀逸です。地球陣営では、エアリーズ社の思惑とは別に、勝手に国連機関が停戦をしてしまうルールが秀逸です。
先日、わたしはエアリーズ社側を持ってプレイしたのですが、腰抜け政治家の軟弱な決議を和平会議の行われている木星の基地ごと爆撃して粉砕しました‥(^_^;
あとはゲームを実際にプレイしてみてもらうのが良いと思いますが、SFフリークを唸らせる中身を持つ古典的名作です。当時のSFゲーム人気ナンバーワンなのは頷けることでしょう。
バトルフリートマーズの難点
上述のように面白いゲームなのですが、実はこのゲームには全体像としての戦略ゲームの他に、個別の戦闘を解決する戦術ゲームがあります。基本的に戦略ゲームでは戦術ゲームシステムを用いずとも普通のCRT式の解決でサクサクとプレイできます。けれども、その代わりに、それ自体が独立したゲームとも言うべき戦術ゲームシステムを使ってプレイすることもできるのです。
ちなみに、この部分はどうやらSPIのカプセルシリーズとして出た「ヴェクター3」と同じもののようです。
で、そこが問題でして、現実には戦術システムを用いて全体をプレイするというのは無理があります。
ヴェクター3については既に紹介してありますのでそちらを参照してください。こちらも航空宇宙軍史を思い起こさせるサブシステムになっています。
関連ゲーム / 類似ゲーム
関連ゲームとしては戦術システム部分である「ヴェクター3」が挙げられます。
また、規模が太陽系を飛び出してしまいますが、似たようなハイブリッド(戦略・戦術ゲーム構成)を持っている作品に同じSPIの「スターフォース」があります。
太陽系内の戦闘ゲームとしては、GDWの「トリプラネタリー」やSJGの「オービットウォー」もあります。